僕自身は、デッキを組むときにパワーレベルもブラケットも全然気にしてこなかったし、これからもそうだろう。
なぜならば、コミュニティ内で共通の見解があるから。
- 基本的に勝つつもりでデッキを組む
- ルールに則っていれば問題なし
そのため、相手が《タッサの神託者》を使おうとも、長い長いソリティアをしようとも、《人造魔道士、ケフカ》で手札をカラにされようとも、不平はあっても否定はしない
まあ、だいたいは、不平不満も茶化して言うのだが。
しかし、これだけでは十分ではなかったりする。表面的。実は根底には
- みんながある程度の空気を読む
この要素は外せない。
例えばEDHでもデッキ相性があるため、マッチアップ次第で特定のデッキが勝ち続ける。
勝ち負けだけでなく、《血染めの月》で多色デッキを不自由にさせるなど、一方的なゲームもあろう(そして往々にして勝敗よりこちらの不快度の方が問題)。

特定のプレイヤーが苦痛に喘ぐ時間が極端に長いとか、誰か一人だけしか楽しめていない状況が続いた場合には、各々が自発的にデッキを変える。
ゲーム展開は偶発的なもの。不快なゲームは不慮の事故。仕方の無いことである。
それを詫びるでも責めるでもなく「ちょっとデッキ変えるわ」で済ませる。これを互いにやるのだ。
そのため複数の系統の異なるデッキを持つ。最近だと僕はパイオニアEDHのデッキを3個持ち込む。
純粋に別のデッキを楽しみたい意図もあるが、ゲーム展開を変えるために切り替えは大事である。
ちなみにパイオニアEDHの面々でプレイする時も、普通のEDHのデッキを1-2個もつ事が多い。
通常EDHを遊びたい人が居たときに持ってないと困るし、パイオニアEDHの連戦に疲れてきた、飽きてきた時に気分転換として使ったりする。
なんとパイオニアEDH相手に、無情にもデモコンタッサを仕掛けるのだが、これを使う場面も考え無しではない。
単にデモコンタッサつえーを見せつけたいのではなく、たまたま自分の敗北や密度の薄いゲーム展開が続いたときなど、周囲から納得感が得られそうなタイミングで、それまでとは異なるゲーム体験を魅せるつもりで使う。ようは、流れを変える。
よく練られたパイオニアEDHは、普通のEDH相手にも良い勝負をするので、意外と接戦になって、新しい発見をすることもある。
当然だが、《タッサの神託者》で5回も6回も勝つことはない。
通常EDH同士の対戦でも、パイオニアEDHとの異種混合戦でも、2-3連勝したくらいでデッキを変えるのである。
それが僕らのEDHの楽しみ方。
コミュニティの難しさ
僕が本格的にMTGをプレイしだしたのは、中学の同級生との関わりから。
一時期は10人ほどの遊び仲間がいたが、大学受験で自分を含めてほぼ引退し、大学進学後に再開した時には同級生は散り散りとなったため、ほぼ1人の友人と遊ぶ状況だった。
当時はスタンダードとレガシーを遊んでいたため、仲の良い友人一人でもトーナメントに参加するには不具合はなく、プレイするにつれて薄い繋がりの知人友人も増えた。
しかし、これは大会が頻繁に行われるレギュレーションだからこそ出来たことである。
EDHは、基本的には仲の良い友人一人では難しい。
やはり4人対戦が醍醐味。
進学や就職など大きな変化を機に、それまでのコミュニティが崩壊することがある。特に社会人で家庭を持つとゼロから集めるにはしんどい人数である。
しかもEDHの場合は全員同時に予定を開けなければならない。現実には5-6人か、それ以上の人数でコミュニティを維持しないと、4人対戦を行うことは夢物語となってしまう。
普段は2人でスタンダードを遊んでいて、大会に向けて練習をするという遊び方は成立する。大会に出るうちに、常連の人達との繋がりが増えていくだろう。
しかし、普段は2人でEDHをして、大会に向けて練習というのは成立しない。
なんなら、カジュアルEDHでは“練習”ではなく“交流”を求める。
更にEDHの場合は、大会も他のフォーマットほど頻回に行われないし、地域によってはゼロである。
大会をきっかけにコミュニティを広げるということが大変難しい。
じゃあ、自分はどのようにEDHコミュニティを形成できたのかというと、同じショップに通う常連の中で、同じプレイスタイルの人達が引き寄せられて形成された。
そしてショップが潰れた後も、予定を合わせるために何度もやり取りをして定期的に顔を合わせている。
互いに仕事や家庭の事情がある中で、ある意味で頑張って維持している。
正直に言って、最初にコミュニティを作れたのは運である。
もちろん家で寝てたら自然に出来たわけではないので、お店やイベントに足を運んだとか、プレイスタイル関係なく対戦して(そして合わない人達との関係は自然消滅して)、対戦の機会の回数を稼ぐことで、よく似た人達が集まる可能性は広げてきたが、それでもやはり恵まれていたと思う。
しかし、それを維持するのは運ではなく努力である。
4人以上集まるためには、「暇になったら遊びに行こう」という緩い気持ちでは無理。
コミュニティを形成する段階で一つの壁があるが、それを維持する段階でも大きな壁がある。
これはEDHを楽しむ上で付随する、頭の痛い問題である。
(僕はネット上での対戦は一度も行ったことがないので、そちら方面での解決策については語る資格がない。あくまで対面MTGの話である)
共通認識の力
トーナメント志向かカジュアルか、この手のプレイスタイルばかりが注目されるが、EDHを楽しむ上では大事な要素が他にもある。
勝ち負け楽しみ以外の、大事な共通認識について述べる。
時短
有意義なプレイ時間を最大限にするためには、EDHでは時短プレイが必須である。
我々の身内戦ではこのようなやり取りは頻繁にある。
1ターン目の場合
A「フェッチで諜報持ってきてエンド」
B「Aを対象に《対称な対応》使うわ」
A「じゃあトライオームにする」
これを厳密にプレイするなら、Aは全てのプレイヤーのアクションを見てから、自分の直前のプレイヤーのエンド時にフェッチランドを生け贄にし、目的のカードを探さなければならない。
正直1ターン目のフェッチランドで全員が厳密なプレイをやるとゲームが進まない。
そのため特に1ターン目は全員が口頭でやる事を順に話し、ほぼ同時にデッキを探しているのである。
しかし《対称な対応》のようにサーチ先が変わるアクションを起こされる事も稀にある。
その場合、本来適切なプレイで回避可能だった問題については、全ての巻き戻しを許している。
すなわち、省略をしなかった場合、フェッチランドを残したまま全ての相手の行動を見るわけで、《対称な対応》にスタックして生け贄にするのが妥当なプレイ。
ちなみにこれはパイオニアEDHの話なので2-3ターン目くらいまでは「あれを探してエンド」と宣言して相手のターンで探すことは多々ある。
駆け引きが重要になるシーン、例えば《エイヴンの思考検閲者》をキャスト可能な人がいる状態では適当なフェッチ切りはしないが、影響が無いと思われる部分は積極的に省略して巻き戻しをする。
ゲームエンドの場合
これもパイオニアEDHの例を挙げる。
例えば統率者の《偉大なる統一者、アトラクサ》が出ており、手札が充実した状態で《運命のきずな》を唱え、相手に妨害がなく通った場合。

手札に更に6ターン分の追加ターンを得ることが確定している場合(詳しくはデッキ解説を見て)、僕は手札を公開して「今から確定で6ターン行うけど続けるか」と全員に聞く。
《アトラクサ》の統率者ダメージ7点×3で二人倒せるが、厳密には6ターンでは全員を倒せない。
しかし残った一人は、6ターン分のリソース展開をした自分とタイマンになる(しかも最も勝ちの目が少ない人が生き残る)ので、まあ勝てないだろう。更なる追加ターンを引いて勝ち確定になるかもしれないし。
このような実質勝ちの状態では、手の内を公開してゲームの継続を問う。そして基本的には全員合意の上で投了される。
もちろん、厳密には勝ち負けは分からない。万に一つの勝てる可能性があるかもしれない。
しかしごく僅かな確率のために、退屈なソリティアを見続けたいかどうかはプレイヤー次第だろう。
そして僕もそうだし、友人達もそれを望んでない。
そのためほぼ勝ちのパターンが完成した時点で投了をするのである。
一方で、殴り合いの果てに複数人の残ライフが5点となり、かなり厳しい状況だとしても、これだけでは投了はしない。
ゲームの均衡のために誰かが生かしてくれる場面もあるし、大抵そういう場合は泥仕合なのでチャンスもそれなりにある。
むしろギリギリのライフでの接戦はパイオニアEDHでの醍醐味である。まだゲームは終わっていない。
こういう場面では、全員が普通にゲームを続けて、楽しむのである。
さて、とは言ったもののゲームの終局の判断は実はとても難しい。
囲碁の初心者が終わりを判断できないのと同じ。
一見して勝てる見込みがあるようで全然無い場合もあれば、その逆もある。
そしてEDHでは基本的には一人だけ投了は認められず、全員の合意が必要。
コンボと違ってシナジーやチェインでの実質勝ちを全員が理解するには、全員が互いのデッキや使われる戦術に対して理解していないといけない。
勝ち目の判断も同じ。
あのプレイヤーが、あのカードを使えばまだ分からない……それを皆が理解してないと続ける意義を見失う。
先に述べた省略と巻き戻しも同じく共通の理解が求められるが、「ここは省略しても良い」「ここは巻き戻し可能」「この場面では省略が望ましくない」ことを全員が理解していないとスムーズに遊べない。
僕らは互いに情報の共有があり、相手の練度への信頼もあるので、非常に高回転でゲームを行う。
もしも暇で暇で仕方なくて無限に時間があるとか、3人の手を止めてフェッチランドで探している瞬間が最も楽しいというなら好きなようにやればいい。
しかし限られた時間の中で集まり、少しでもゲーム体験の密度を増やすには、徹底的に縮めていく方が良い。
誰かが呼びかけたわけではなく、経験則で自然と短縮されていったのだ。
思考時間
EDHではリソースを膨大に獲得する動きが重要なので、8マナあって手札も8枚みたいに選択肢が非常に多いケースは頻発する。
しかもハイランダーなので、カードの組み合わせは膨大で、対戦相手が三人もいるので影響する範囲を考えるのも大変だ。
じっくり考える場面も時にはあるが、多くの場合、僕らは即決する。
それは一人プレイである程度の動きは理解している前提だし、相手のデッキの(それが例え新デッキでも)動きはある程度のパターン認識出来るくらいに経験があるし、相手のターンの間に次の自分の行動を考えておくから。
そして結構重要なんだが、多くのプレイヤーが即決派。
熟考してもそんなに変わらないことも多く、複雑な盤面であるほど浪費する時間に成果が見合わない。
結果的に間違いがあったとしても「うわー、ミスったわー」で終わるだけ。大会ではないのでそれで良いと思っている。
直感で90%の精度、熟考で95%の精度だとしたら、迷わず直感を選ぶ(考えたところでミスはゼロには出来ないし、経験を積んだ直感は結構当たる)。
確かに駆け引きや緻密なプレイを楽しむ場面もあるのだが、僕らの中では多くの場面で時間の短縮が意識され、それが共通の認識でもある。
インスタントなEDH
大会が少ないとは言え、大型イベントではサイドイベントでの交流会が頻繁にある。
今やセット毎に統率者限定のカードが刷られていることから分かるとおり、EDHは人気フォーマットなので、足を伸ばす覚悟があれば、その日限りのプレイが可能。
しかし、ここで大きな問題が立ちはだかる。
プレイスタイルの違いである。
大会ではなく交流会だと、必ずしも勝利至上主義が求められるわけではない。
初対面同士で一方的なゲーム展開にならないようにするためには、合わせるために何らかの目安があった方が良いかもしれない。
「かもしれない」という言い方になるのは、コミュニケーションを取れば必須ではないと思うからである。
自分は交流会にはあまり行かないが、友人達と行くこともあった。
そうすると例えば友人の何人か他のイベントに参加していて、3人で卓を囲んでいるときに、混ぜて欲しいという孤高の挑戦者が現れることがある。
勿論僕らのプレイを見て参加なので、ある程度のスタイルが合っているという見込みで始めるが、どうしてもパワー格差を感じるゲームはあった。
コンボで一方的に勝ってしまうとか、僕らの構築に“追いついていない”と思った場合、僕らは持っているデッキの範囲で格下げする。
それで良い勝負が出来れば何度か遊ぶし、難しそうな場合は挑戦者が諦めて退室する。
別に文句を言い合うわけではない。
手持ちでは合わせることが出来なかったなら、お互いに礼を述べて、デッキの話などしたりしなかったりして解散となるだけだ。
では逆に僕は自分一人で他のグループに参加したり、見知らぬ4人と交流戦をするのか?
答えはNOである。理由がある。
稀に大会には出るが、交流戦には必ず同卓に友人が入る場面でしかやらなくなった。
一つには、勝敗にこだわるプレイスタイルが違う場合に、面倒な言い掛かりを付けてくるプレイヤーがいると不快であるため。
大会ならば少なくとも自分のデッキやプレイスタイルを否定されることはない。
しかし、その大会もあまり出ないのだが、省略の共通見解、プレイの時短など、快適にプレイする要因が噛み合わないことが多いため。
大会に参加するくらいなら、自分のデッキくらい使いこなして欲しいと思うが、実際にはそのデッキを全然使ったことがないのか、悩む必要が無い(と経験ある人は思う)場面で急に長考する人がいる。
考えに考えた末に《死の国からの脱出》を置いて、そこから一人で膨大な時間をかけてソリティアをするのである。勝ちきれるはずなのに時間切れになって引き分けになるのを見ると滑稽でもあるが、全体的な体験としては……。
僕としては、貴重な遊べる機会に、鈍くさいプレイを眺めて終わるのは嫌なのである。
そんな毎週のように時間を取れるわけではない。
僕も妻も共働きで休日にも仕事がある場合もあって、幼い子供もいるため、遊びに出掛けるには仕事と家庭内の調節だけでも相当な労力が必要。
だから、滅多に大会には出ない。交流会にも行かない。
EDHでは見知らぬ人との対戦に潜在的なストレスが多すぎる。
しかし、見知らぬ人と対戦しない、と強気に言い切れる背景にはコミュニティがあるからである。
これを作れなかった場合には、見知らぬ人との対戦こそが唯一のプレイ機会である場合もあるだろう。
その時に、対戦相手と“合わない”ことでストレスを抱えるのは、誰にとっても気分が良くない話である。
それに僕の幸運もいつまで続くか分からない。
何が引き金で今の環境が崩れるか分からないし、そんな時には、やっぱり気兼ねなくイベントに参加できる優れたシステムはあって欲しいと願う。
ブラケットに足りないのは客観性
よくある言説について、もう少し補足する。
心理学の分野では、何かの専門家の判断とアルゴリズムによる判定基準の、どちらがより正解を導く確率が高いのか、既に概ねの結論は出ている。
すなわち、よくて同等、基本的にはアルゴリズムの方が優れている。
専門家といえど人間であり、バイアスや思考の偏りは避けられない。自分で気付くことが出来ないからこそバイアスなのである。
そのため専門的な分野の中には、客観的に点数付けをして、その結果によってその後の指針を変えるというアルゴリズムに頼る分野が多いと思う。
もちろん、そのアルゴリズムもデータに基づいた検証と、作成後に有効性を確かめなければならないのは当然のことだが。
日常的な話で言えば、投資をする時に、タイミングを見るとかこれは買いとか売りとか考えるよりも、事前に決められた基準通りに売買を進める方が平均的なリターンが高い。
アクティブ運用(積極的な売り買い)で儲けられるのはごく一部であり、アクティブ運用である一年に儲けた人も翌年どうなるのか分からない。
平均的な伸び率が高いのはインデックス投資であるというのは今や常識であろう。
それを知った上で僅かな望みに賭けて大当たりを狙う(そして高い確率で大損をする)こと自体は個人の選択なので好きにすれば良いが。
話は逸れたが、EDHでクラス分けする際にも主観が入らない、客観的なアルゴリズムに基づいて分類の方が、おそらく良い結果を生み出しやすい。
不確定要素の多い分野こそ、個人の思考はバイアスに塗れるため、アルゴリズムが役立つ。
ブラケット・ソムリエなる資格が生まれ、厳しい試験をくぐり抜けたソムリエのみが分類できるとしても、アルゴリズムの方が良い結果を招くだろう。
ましてや、僕らの行うブラケットの分類は、ド素人の経験則。
世の中で、もっとも信用ならない行為である。ド素人の経験則だよ?
素人では無いという人は、ブラケットに対してどれほど客観的な検証を積み重ねたのか教えて欲しい。
勘違いしないで欲しいのは、EDHの素人かどうかの話ではない。ブラケットという仕組みについてである。
さて、パワーレベルの時代、僕は過去の記事で点数付けの可能性について述べた。
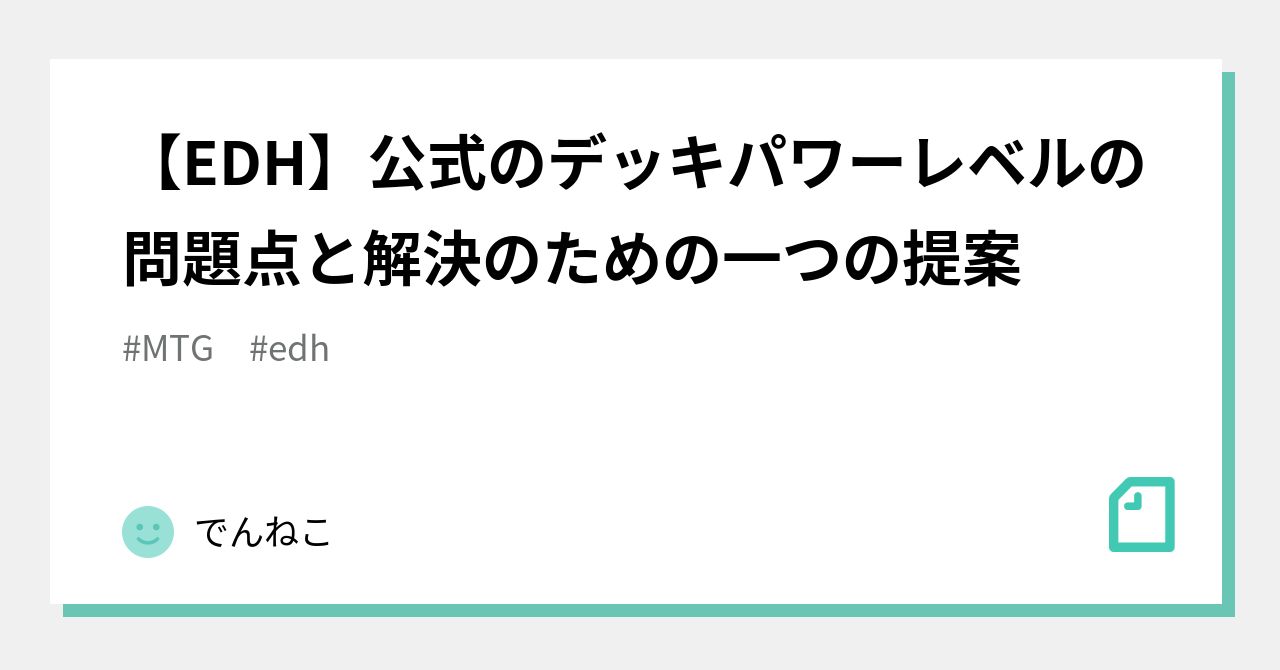
今は環境が違うので同じ点数の付け方は出来ないが、考え方としては今でも凄く納得がいく。
公式は、いつまでも答えのない主観論を積み重ねるのではなく、データによって裏打ちされたアルゴリズムを作るべきではないか?
そういう意味で、ゲームチェンジャーの概念は評価する。
ここには主観が一切入らないので、不満を抱えても揉める余地がない。
構築理念で分類は、正しく分類できるならば最も有効だが、主観評価では永遠に火種になる。
それこそジョジョから引用するから『完璧な作戦』なのである。『不可能だという点に目をつむれば』
さっさとブラケットはパワーレベルとやってることは大して変わらない失策だったと認めた方が良い。
ゲームチェンジャーは見込みがありそうなので、この方向で新しいシステムを作る、ってね。
ただ《セラの聖域》と《古の墳墓》が同格とは、やはり思えないわけで、複雑になっても良いから細かく点数付けして、デッキリストをぶち込んだら自動的に点数が出るくらいの方が良いのよ。
即席の解決策
さて、そうは言ってもデータの積み重ねは一朝一夕にいかない。
航空業界が長い年月と事故を積み重ねてチェックリストを研ぎ澄ませ、最高クラスの安全を提供する分野に昇華したように、専門家と試行錯誤が必要だ。
目の前の問題はどうすればいい?
そこで良いシステムが出来るまで、即席の妥協案を考えたい。
ゲーム体験を高めるためには
- 勝利への拘りが同程度
- 時短への理解が同程度
- デッキの相互理解が同程度
- 思考時間に対する考え方が同程度
これらが重要と話した。
これは気心の知れた仲間内ではすり合わせ可能だが、知らない相手、しかも4人全員が満たすことは現実的には不可能である。
つまり初対面の相手とEDHをプレイすると、絶対に不快になる。
不快にならなかった場合、奇跡的に上記の4つが揃ったか、誰かが相応の我慢をしている。
せめて勝利への拘りだけでも近い位置に合わせようとするのが、パワーレベルだったりブラケット制度なのである。
時短や知識量は、客観的に推し量ることは出来ない。ここのすり合わせは最初から諦められている。
制限時間のある大会ですら、気にせず時間を浪費するプレイヤーがいる(そして自分の勝つための時間も失う)のだから、将棋のように各プレイヤーに手持ち時間を設けるルールにしないと、思考時間の短縮に関しては叶わない。
こういった勝ち負けだけで議論できない不快な部分が、現状の決め事では、どうしても残る。
いいか、もう一回言うぞ。
初対面の相手とEDHをプレイすると、絶対に不快になる。
これはまさに人間関係そのものなんだ。
手段の多くを共有できている仲間同士と違って、見知らぬ人との間には多くのすれ違いが起きる。
それらを我慢したり、伝えたり議論することで合わせていく。
『ブラケットを守っている自分が不快なのは、相手のせい』という狭い視野での他責思考が強いと、揉めるのである。
『僕ちんを不快にさせた相手には何を言っても良い』そんな考えでは成り立たない。それが多人数戦。
ブラケットは、相手と調整すべき一つの要素でしかなく、単独で絶対的なものではない。他にも目を向けてくれ。
そもそも自分の嗜好に合う友人やコミュニティを持つ人には無用の長物。
なぜブラケットがあるのか、それはブラケットに頼らなければ満足にマッチング出来ない人への施しだから。
炊き出しを利用するなら表面上だけでも良いから感謝と礼儀を尽くせ。
僕は今のところブラケットなんて使わないからボロクソに言うけど。
しかし、足りないとか無駄とだけ話すのもまた、役に立たない論説である。
てめーの改善案はないのか?
色々と考えてみた。
結果、ブラケット3で遊ぶ場合のみ、ある質問に対する答えの○×を後に付ければ、より満足のいくマッチングが出来るのではないかと思った。
一番揉めるのはブラケット3だから、ブラケット3×とか、ブラケット3○と言って欲しい。
これは全ての人を救済するわけではない。
一部の人達に非常に有利な分類となり、救われぬ者たちは、より濃縮されたトラブルが起きるだろう。犠牲はやむなしである。
間口を広げたい公式としては、当たり障りのないルールで広めたいだろうが、客観的なアルゴリズムを作らない限り、いつまで経っても堂々巡り。
パワーレベルとかそれ以前のガチカジュ論と同じで、いつでも皆は立ち止まって議論をしている。もはや不満たらたらでEDHをプレイするより楽しそうに見える。
僕の考えた質問はシンプルである。そして納得感もあると思う。前にも進めるだろう。
それは……
あなたは童貞ですか?
これに対して○×を付ける。
素人とか玄人とか、年齢によって重みが違うとか、同姓はアリですか、など言い出すと切りが無いので、とりあえずシンプルに考えてくれ。
ブラケット3×同士、ブラケット3○同士でマッチングすることで、きっと多くの卓で“成功”するだろう。
そして、これを読んで腸が煮えくり返るような怒りを抱き、X(Twitter)で批判コメントをする人はいるはずだ。先に謝っておく。申し訳ない。
僕もただのオタク童貞だった頃には、こういう言葉にはとても敏感だった。
だが、少し待って欲しい。
今の心の中に浮かんでくる負の感情は、おそらく見知らぬ人とのEDHのプレイの中でも一定の確率で発生する。
相手と意見や立場が違うとはそういうことなのだ。
ルールメーカーでも何でも無い僕の戯れ言など無視すれば良い。
それを読んで、怒り狂って行動してしまうようでは、EDH対戦も冷静に出来ないだろう。
あなたが紳士的にEDHをプレイするのと同じように、心の内に留めておいて欲しいものだ。
もちろん、中には○×に嘘をつく人もいるかもしれない。
しかし、それはそれで構わない。
嘘をついているという引け目が、その人の暴力的な行動に対する抑止力になるだろう。
そもそも○×が真実かどうかは関係ないのだ。あくまで目的はEDHの対戦での衝突の回避や軽減である。
ちなみに、質問の仕方は変えない方が良い。
○と×に本質的な違いは無く、単に区別する記号なのだが、非童貞は×を付けられても何も思わないのに対して、童貞が自分に×というネガティブな記号を付けることは抵抗感があるだろうから。
むしろ☆と×でも良い。
ブラケット3☆
良い響きだ。
もしも個人情報を明らかにしたくなければ、自分がブラケット3と思っているデッキを持ってブラケット4にいけばいい。
以前に書いたが、僕らはブラケット4のハードルを勝手に上げているだけで、自称ブラケット3の中にはブラケット4相当がいるのである。
勝手にブラケット3という枠組みに治まってないで、一歩踏み出してほしい。
ブラケット3から4に踏み出す勇気に匹敵する“少し嫌な気分になる”質問をブラケット3に仕込むことで、釣り合いを取るのだ。
まとめ
もっともらしく話したが、こんなのネタである。
ブラケット論争とはそれほど下らない。
ではまた。

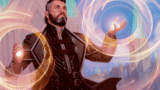
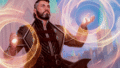

コメント